石田正澄。石田三成のお兄さんです。
しかしこの人、個性がわかりづらいと感じるのは私だけでしょうか。
なにせ、よく知られている人生のハイライトが、関ヶ原の戦いの際、三成の居城、佐和山城を守備したというところです。
そもそも、この籠城戦は一族総出で行われたものですから、石田家自体が三成ありきの一家だったのではないかというイメージがあります…。
ですが、そんなイメージを持ったままなのも申し訳ないので、今回くわしく確認してみることにしました。
果たして弟の七光りという私の勝手なレッテルは払しょくできるでしょうか。
教養人の父のもとで育った石田兄弟
改めまして、石田正澄。石田三成の兄。生年はよくわかっていません。
ですが、母親は三成と同じ瑞岳院さんと言われていますので、まぁ、彼とそんなに離れてはいないでしょう。(三成は1560年生まれ)。
父、正継の次男。長男は早世したようです。
父の石田正継は近江坂田郡石田村出身の地侍、または、京極氏の被官といわれています。
が、出自には諸説あり不明です。
木曽義仲の討伐で功績のあった石田為久の末裔だというものや、崇神天皇皇子・豊城入彦命の後裔を称する下毛野氏の一族である、などの説があります。
正継のお父さんには、前陸奥入道清心、お祖父さんには、前蔵人入道祐快、という法号が残されていますので、少なくとも、主君である秀吉のようなぽっと出のお家の人、というわけではなさそうです。
正継は学問の志高い人で、和漢に通じ、万葉集に造詣のある才人でした。お寺から60巻もの書籍を借りてきて読破し、三成にも読ませようとしたといいます。
石田三成と豊臣秀吉の出会いのエピソードである「三献茶」という逸話があります。
鷹狩帰りにのどが渇いた秀吉がお茶を所望したところ、一杯目はのどを潤すためにぬるめのお茶を。二杯目三杯目はお茶をゆっくり味わえるように徐々に熱くしたものを出す。というまるで漢籍にでも出てきそうな逸話です。
これは創作という説もありますが、こんなエピソードが創られるのもうなずける家庭環境だったようですね。
弟は秀吉の側近、兄は実務派の官僚

さて、石田兄弟は1577年(天正5)に羽柴秀吉が中国征伐の総大将に任じられた頃、兄弟そろって秀吉に士官しました。
弟、三成は秀吉の側近として台頭していく一方、兄、正澄も実務派の官僚として、各地の代官、奉行などを歴任するようになります。
- 1583年(天正11):近江高島郡の代官に任命。河内国の蔵入地※1の代官も兼務。
- 1584年(天正12):小牧・長久手の戦い。近江長浜から鋤や鍬を前線の尾張犬山に輸送する町衆を監視する役目にあたる。
- 1589年(天正17):美濃国の検地に従事。
- 1591年(天正19):豊臣秀吉、翌年春に「唐入り」を宣言。九州の諸大名に対し、肥前名護屋に城を築くことを命じる。石田正澄も早くに現地入りし、秀吉のための茶室を建設する。
- 1592~1593年(天正20~文禄2):文禄の役。朝鮮半島への物資の輸送や、石田三成、大谷吉継、増田長盛ら渡海した奉行衆から上がってくる報告の取次役を担う。
- 1593年(文禄2):従五位下木工頭に叙任。豊臣姓も下賜される。同じ頃、堺奉行にも就任。
- 1595年(文禄4):豊臣秀次切腹事件※2勃発。これを受けて「御掟」「御掟追加」が制定。同時に、訴訟事を担当する奉行衆が新設され、正澄もそれに名を連ねる。
- 1597~1598年(慶長2~慶長3):慶長の役。秀吉の奏者として、伏見に残留。多数の書状を残す。
- 1598年(慶長3):京都醍醐寺にて「醍醐の花見」が催される。秀吉の側室、松の丸殿(京極竜子)に随行。
- 1598年9月18日(慶長3年8月18日):豊臣秀吉没。享年62。
- 1599年(慶長4):秀吉の後継者、豊臣秀頼の側近に。五大老五奉行の連署にて、片桐且元らとともに、秀頼の奏者番となる。
【用語解説】
※1:蔵入地(くらいりち)
大名もしくは政権、幕府の直轄地のこと。代官を派遣して直接支配を行い、年貢・諸役などの徴収にあたらせる。朝廷における「御料所」と同義。豊臣政権の蔵入地は太閤蔵入地(たいこうくらいれち)とも呼ばれ、最盛期には畿内を中心に220万石に及んでいた。
※2:豊臣秀次切腹事件
1595年(文禄4)、秀吉の甥で関白である豊臣秀次が「謀反を企てた」という理由で突然自害に追い込まれ、一族郎党や多くの家臣たちも処刑されてしまうという事件。本件によって豊臣政権に大きな混乱が生じ、後の豊臣家滅亡の一因になったと考えられている。
このように、石田正澄は弟、三成の活躍とは関係なく、優れた民政家として、秀吉に評価されていたようです。近江に1万5000石(のちに河内国1万石を加増されて2万5000石に)の知行を与えられていた大名でもあります。
また、彼は当時を代表するさまざまなジャンルの超一流知識人たちと交流があったようです。
たとえば、大村由己、藤原惺窩、猪苗代兼如、西笑承兌などの面々があげられます。
【人物紹介】
- 大村由己(おおむら ゆうこ):著作家。豊臣秀吉の祐筆で、秀吉の伝記「天正記」の著者。
- 藤原惺窩(ふじわら せいか):儒学者。近世儒学興隆の祖。林羅山の師。
- 猪苗代兼如(いなわしろ けんにょ):連歌師。明智光秀が本能寺の変の直前に開いた連歌会「愛宕百韻」に参加。伊達家臣。
- 西笑承兌(さいしょう じょうたい):臨済宗の僧。豊臣秀吉の側近で文禄・慶長の役の外交交渉に関与。
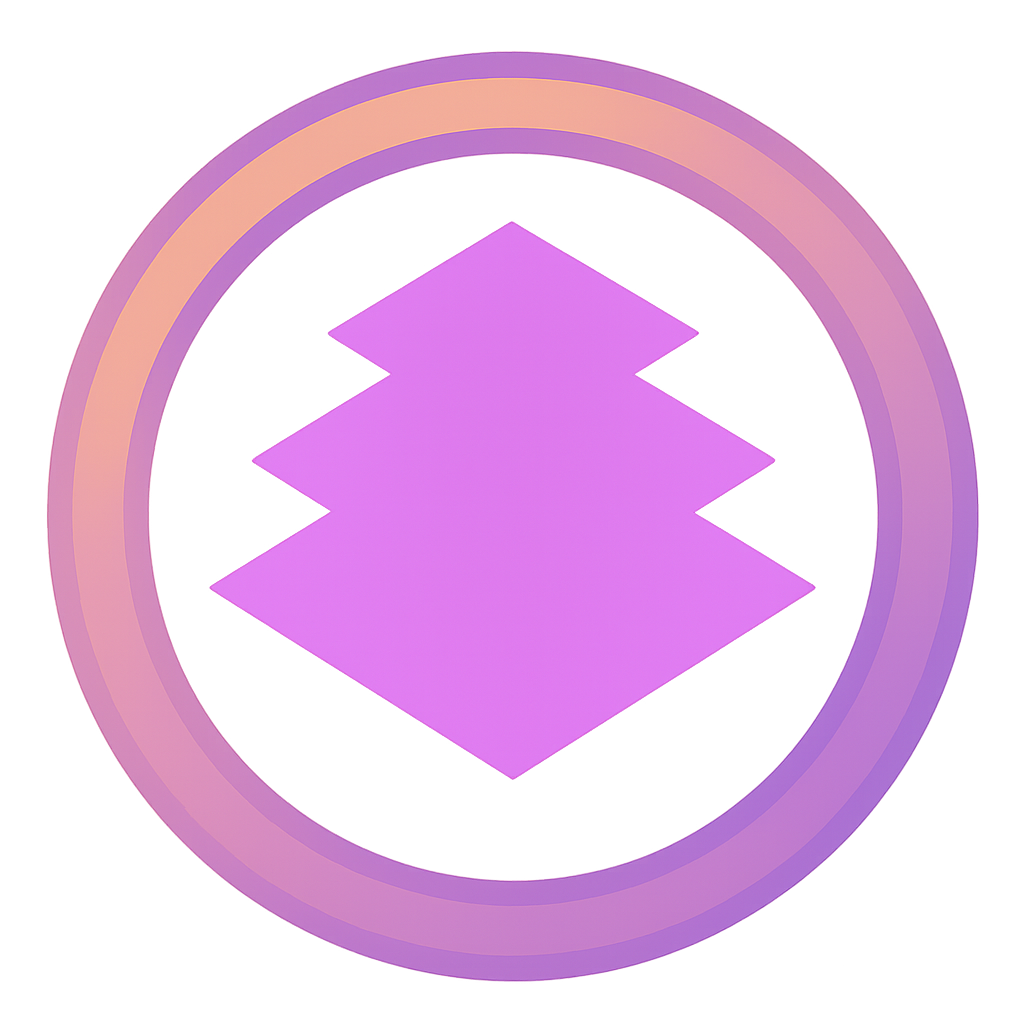
由己や惺窩とは特に親交が厚かったようですね。1594年に石田兄弟の母、瑞岳院が亡くなっていますが、彼らが追悼文を送ってくれています。
弟と志同じくして迎える関ヶ原

そして、1600年(慶長5年9月)、ついに関ヶ原の戦いが始まります。
石田正澄は、父や長男・朝成らとともに三成の居城、佐和山城を守備します。
佐和山城は建久年間(1190~1198年)の文書にも名前が見える古い城で、畿内と東国を結ぶ要衝の地にありました。
戦国時代でも、浅井時代は磯野員昌、信長時代は丹羽長秀、秀吉の支配下に置かれてからも、堀秀政→堀尾吉晴と、それぞれの勢力の重臣が任される重要な拠点とされています。
1595年(文禄4)に、三成が佐和山城主に任じられると、城の大改修が行われます。
元々の佐和山城は、鎌倉時代に築城された城なだけあって、砦規模の山城だったようですが、この改築によって、五層(三層説もあり)の天守がそびえたつ近世城郭へと変貌を遂げました。
「三成に 過ぎたるものが二つあり 島の左近と 佐和山の城」と謳われていたのは有名な話ですね。
もっとも、三成は秀吉の側近として伏見にいることが多かったので、父の正継が城代として、城の管理や領民たちの面倒を見ていたと伝えられています。
民政に関して残されている文書も、三成のものより正継の名のものの方が多いようです。
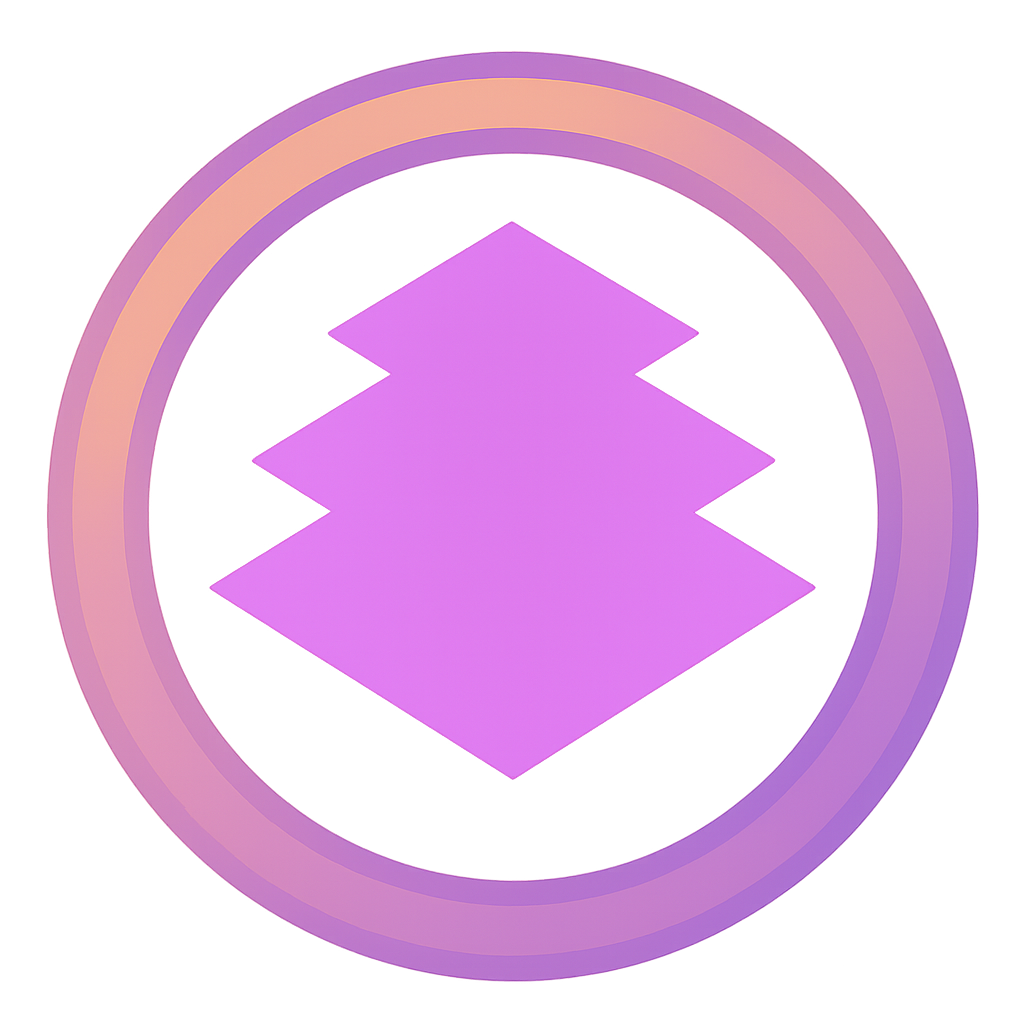
ですので、有事発生時、彼らが佐和山城を守るのは、ごく当然のこと。…三成ありきとか言ってごめんなさい^^;
1600年(慶長5年9月15日)、関ヶ原の地にて、東西両軍の主力がついに激突。
通説では、西軍側がやや優勢の戦況だったところ、小早川秀秋らの裏切りによって総崩れになったと言われています。
大勢の武将が討死や敗走をする中、石田三成も再起を期して伊吹山に逃れました。
徳川家康はその日のうちに、佐和山城攻略を命じ、すぐさま進軍。翌16日には15,000もの大軍が佐和山城を包囲します。
一方の城方は、大坂からの援軍である長谷川守知(茶人・長谷川宗仁の子)の兵も含めて2,800ほど。しかも、石田家の主力部隊のほとんどが関ヶ原に出陣してしまっているため、その多くが老兵だったといいます。
佐和山城攻略を命じられたのは、小早川秀秋、脇坂安治、朽木元綱ら、関ヶ原内応組の武将たち。どうしてもここで戦功を上げる必要がありました。
大軍に加えて士気も高い攻め手を相手に、城方は奮戦。しかし、関ヶ原での西軍の敗戦を知り、正澄は降伏を決断します。
交渉の結果、彼の自刃と引き換えに、他の一族や城兵、女子供は助命するという条件で交渉が成立した、のですが…。
17日明け方、実は東軍側の間者だった長谷川守知が城内に小早川軍の兵を引き入れて三の丸を陥落させると、翌18日早朝には、田中吉政隊が天守に攻め入り、佐和山城は落城してしまいました。
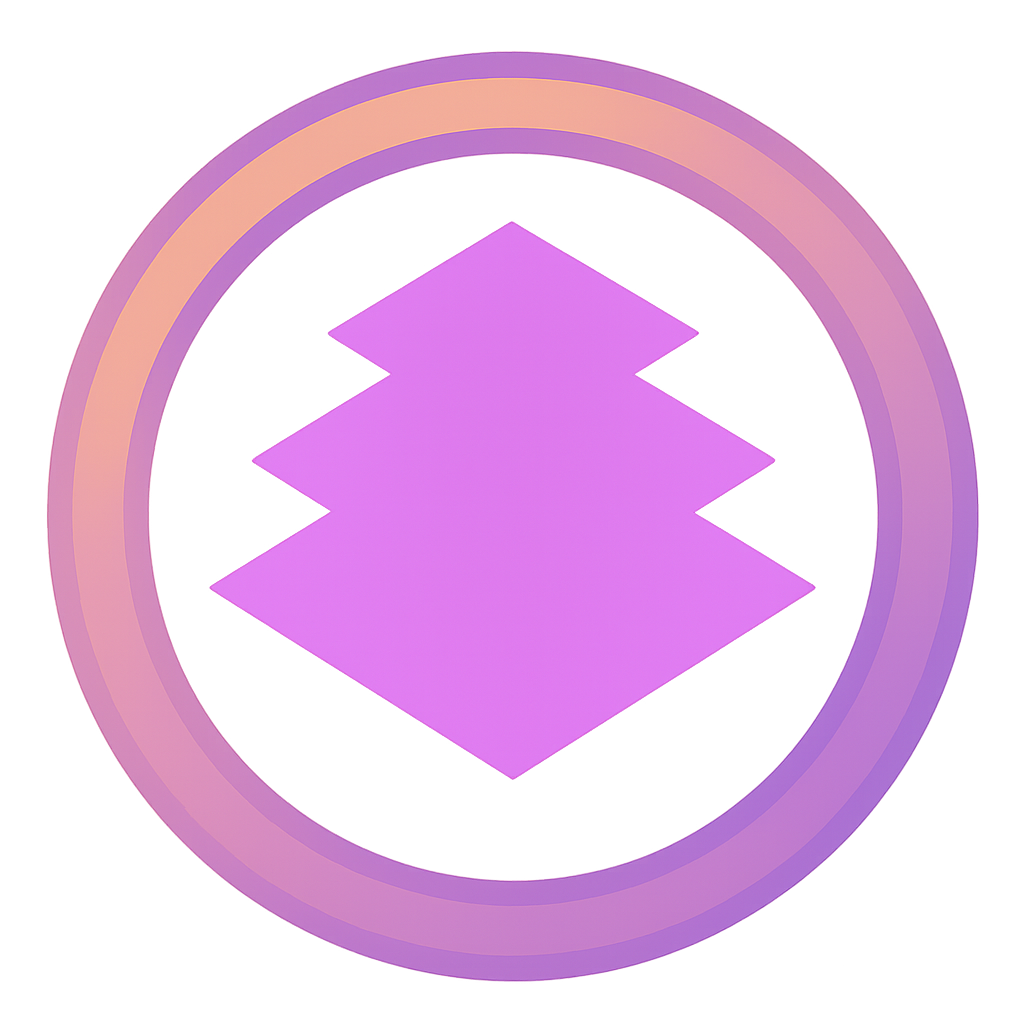
…いやぁ、さすが家康。やり方がきたな、もとい、ぬかりない。
石田正澄は、正継、朝成とともに、自刃して果てます。その他、三成の妻・皎月院や、その実家の宇多頼忠、頼重親子らも命を落としました。
石田三成も9月21日にとうとう捕縛され、見せしめで晒された挙句、10月1日に京都の六条河原で処刑されてしまいました。享年41。
辞世は「筑摩江や 芦間に灯す かがり火と ともに消えゆく 我が身なりけり」。
まとめ
- 石田正澄(生年不詳~1600年)。石田三成の兄。数多くの知識人らと交流を持った教養人。
- 豊臣秀吉のもとで各地の代官、奉行を歴任。実務派の官僚であった。
- 秀吉の死後、秀頼の側近に。生前の秀吉からの信頼も厚く、叙任や豊臣姓の下賜なども受けている。
- 関ヶ原では、弟の居城、佐和山城を一族率いて守備するも、武運拙く自刃。
というわけで、弟の七光りうんぬんは全くもって私の誹謗中傷でございました。この度は誠に申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げますm(__)m
石田正澄は教養深く、堅実な仕事ぶりの能吏でした。今後は弟と一緒くたにせず、きちんと個別に任務を任せてあげたいと思います。
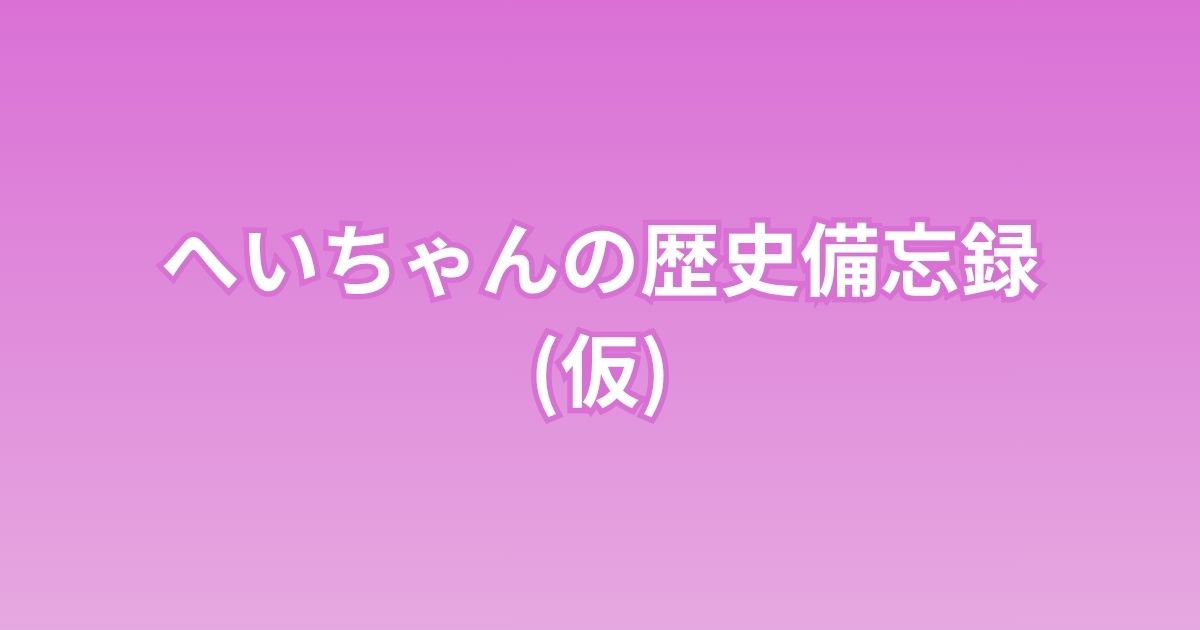
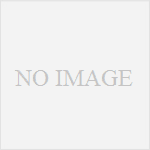
コメント